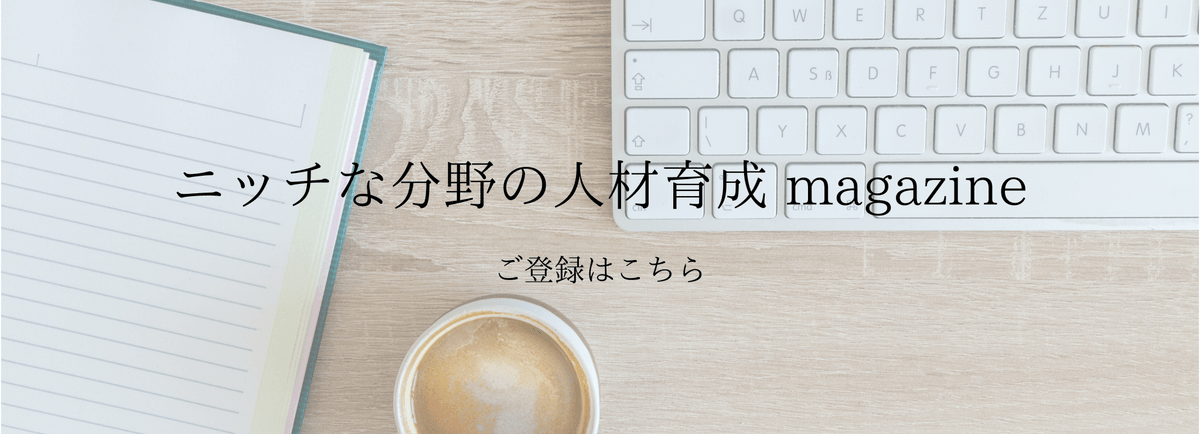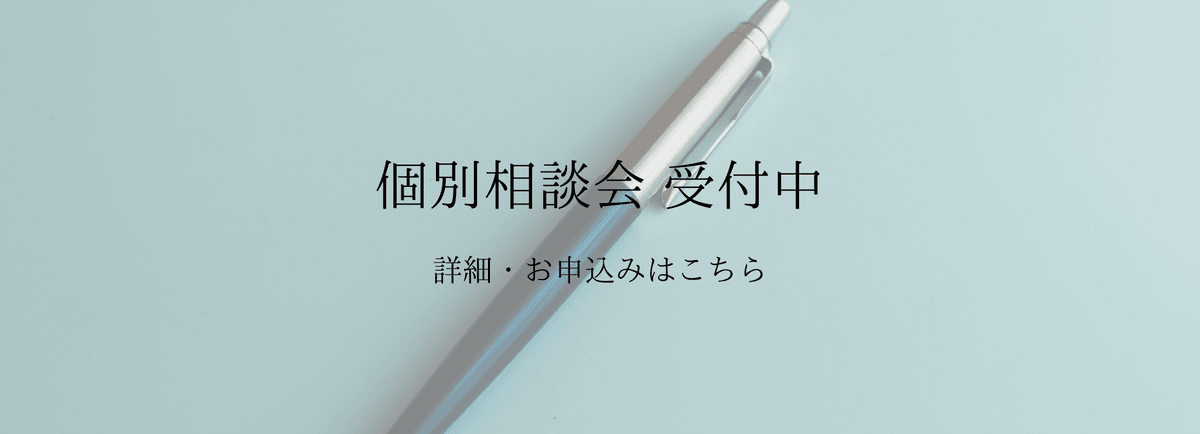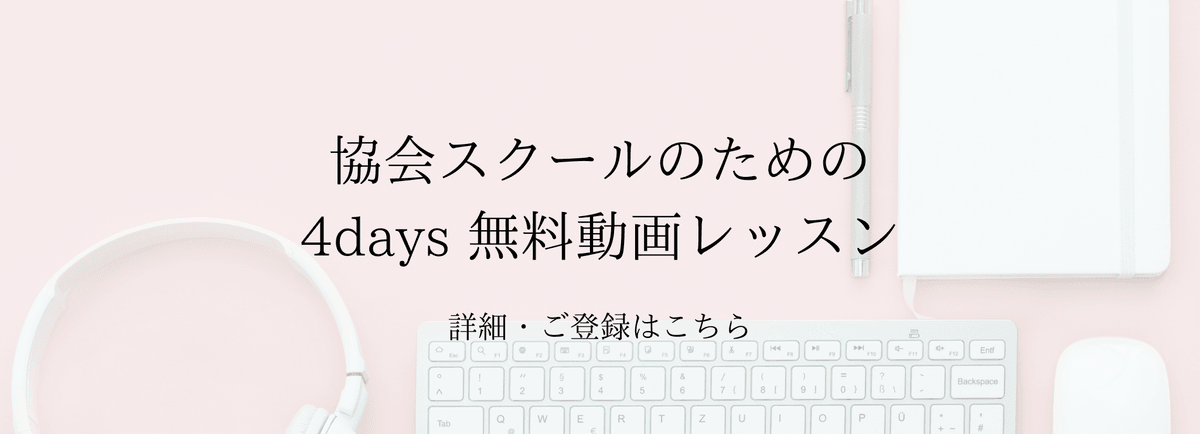こんにちは。
株式会社びぶりあの矢澤です。
今回は「人材育成ノウハウ」について、
少し本質的なお話をしてみたいと思います。
借り物のノウハウでは、ニッチな人材育成はできない
世の中には、
汎用的で広く使える
人材育成のフレームワークや
マニュアルがたくさんあります。
たとえば、
新人研修や営業育成、
リーダーシップ開発など。
こうした
“よくある育成テーマ” であれば、
既存のノウハウを参考にしても
うまく活用できる場面が多いでしょう。
ですが、それが
「ニッチな分野」であるならば、
話はまったく変わってきます。
なぜなら、
ニッチな分野には、
必ずその組織特有の
事情・文化・価値観があり、
「何を教えるべきか」も
「どう育てるべきか」も、
個別具体性がとても高いからです。
そのため、
ニッチな分野の人
材育成に取り組むときには、
どこかから “借りてくる” ことではなく、
自分たちの中にあるノウハウと向き合う
ことが重要になります。
具体的には…
- 自分たちの現場で、本当に必要とされる行動や判断とは何か?
- その背景にある考え方や価値観はどこにあるのか?
- その力は、どうやって育まれてきたのか? 育てられるのか?
こうした問いを通じて、
固有のノウハウを言語化し、
体系化していくプロセス。
それが、ニッチ分野における
人材育成の “設計” なのだと思います。
もうひとつ大切なのは、
「自分たちの組織がどれだけニッチなのか?」
ということを、
冷静にかつ客観的に
自覚することです。
「うちは結構どこにでもあるような業種で…」
と思っていても、
実は育成対象となる “役割” が
かなり特殊だったり、
新人の入り方や
経験値がバラバラだったり。
そのような「暗黙のニッチ性」に
気づいていないケースもあります。
だからこそ、
形式知化(言語化と体系化)の前提として、
まず
「自組織のニッチ度合いを見極める」ことが
大切な出発点になるのです。
これまでにない育成の仕組みをつくるには、
これまでにない “問い” と “見方” が必要になる。
そう実感する日々です。
・・・
本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました!